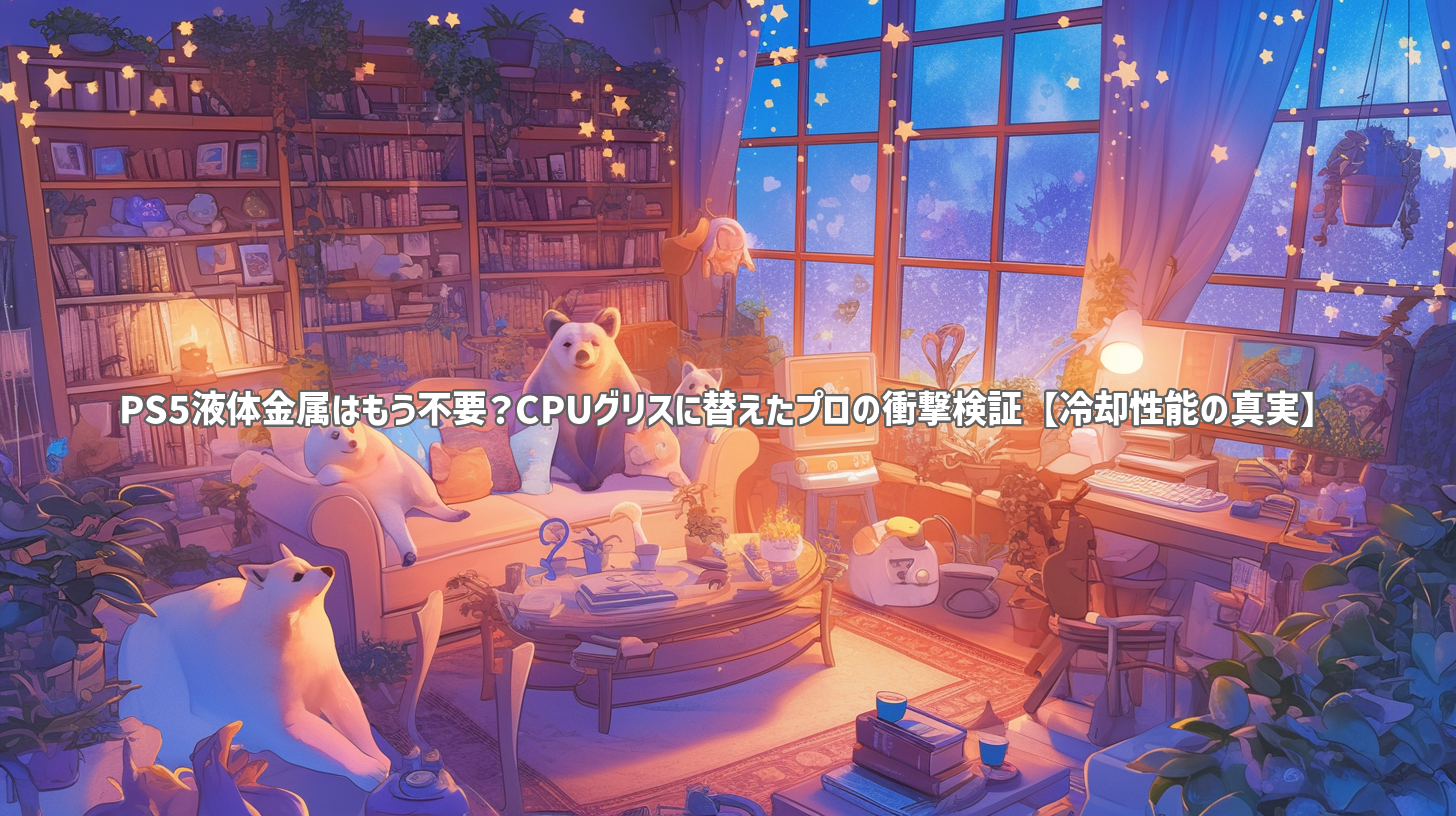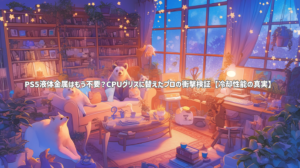PlayStation 5の冷却システム、特にCPUとGPUの熱を効率的に排出するために採用されている「液体金属」は、その高い熱伝導率で知られています。しかし、その一方で、経年劣化やポンプアウト現象、さらには漏洩リスクといった潜在的な課題も指摘されてきました。そんな中、ゲーム機やPCの修理・メンテナンスを手掛けるプロフェッショナル集団が、PS5に標準採用されている液体金属を一般的な高性能CPUグリスに交換し、その冷却性能を徹底検証するという驚きの動画を公開しました。
今回ご紹介するのは、まさにその疑問に真っ向から挑んだ動画「PS5の液体金属…..とりあえずやめますわ~!~PS5をCPUグリスにしてみたって話!~」です。この記事では、この動画がなぜ今、多くのPS5ユーザーやPCエンスージアストから注目を集めているのか、その内容を深く掘り下げ、関連する背景情報やチャンネル「PCER24」の魅力まで、詳細に解説していきます。PS5の冷却性能の真実に迫る、必見の検証結果とそのプロフェッショナルな考察を、ぜひ最後までお読みください。
話題の動画はこちら!
動画の基本情報サマリー
- チャンネル名: PCER24
- 公開日: 2025年07月26日
- 再生回数: 約109,301回
- 高評価数: 約2,150件
- コメント数: 約263件
- 動画の長さ: 17分23秒
動画内容の詳細なレビューと見どころ
この動画は、PS5の冷却性能に関する長年の議論に終止符を打つ可能性を秘めた、非常に示唆に富む内容となっています。PCER24のプロフェッショナルな視点と、徹底した検証プロセスが随所に光ります。
液体金属の「光と影」:なぜプロは交換を決意したのか
動画の冒頭で、PCER24はPS5に採用されている液体金属の特性について言及します。液体金属は非常に高い熱伝導率を誇り、理論上は優れた冷却性能を発揮します。しかし、その一方で、経年によるポンプアウト(液体金属がヒートシンクとチップの間から押し出されてしまう現象)や、誤って基板に付着した場合のショートリスク、さらには塗布の難しさといった運用上の課題も抱えています。
PCER24は、プロの修理業者として多くのPS5を扱ってきた経験から、これらの液体金属の「影」の部分を熟知しています。特に、長期的な安定性やメンテナンス性を考慮すると、一般的なCPUグリスの方が優位性があるのではないか、という問題意識が今回の検証の動機となっています。彼らは「とりあえずやめますわ~!」という衝撃的な宣言と共に、その仮説を検証するために、Arcticの高性能CPUグリス「MX6」への換装に踏み切ります。
プロによる精密な交換作業と細部へのこだわり
動画の中盤では、PS5の分解から液体金属の除去、そして新しいCPUグリスの塗布に至るまでの一連の作業が詳細に記録されています。特に注目すべきは、液体金属の除去作業の丁寧さです。残存する液体金属が基板に付着しないよう、細心の注意を払ってクリーニングを行う様子は、まさにプロの仕事。この工程の重要性を、彼らは視聴者にも分かりやすく解説しています。
また、グリスの塗布方法についても、単に塗るだけでなく、均一に薄く広げることの重要性や、グリスの特性を最大限に引き出すためのコツが語られます。こうした細部へのこだわりが、後の検証結果に大きく影響することを理解させてくれます。
衝撃の検証結果:液体金属 vs CPUグリス、冷却性能の真実
今回の動画の最大のハイライトは、液体金属からCPUグリスに換装したPS5が、実際にどのような冷却性能を発揮するのかを数値で示した点です。PCER24は、人気ゲーム「God of War Ragnarök」をプレイし、CPU、GPU、メモリ、VRMといった主要コンポーネントの温度を詳細にモニタリングします。
驚くべきことに、検証結果は多くの視聴者の予想を裏切るものでした。液体金属を使用していた時と比べ、CPUグリス(Arctic MX6)に換装した後も、主要コンポーネントの温度はほとんど変わらない、あるいは場合によってはわずかに低下する傾向すら見られたのです。ファン回転数も同等レベルに保たれており、冷却性能が著しく低下するという懸念は完全に払拭されました。
この結果は、「熱伝導率の数値だけがすべてではない」というPCER24の主張を強力に裏付けるものです。グリスの塗布状態、ヒートシンクとの密着度、そして長期的なポンプアウト耐性など、総合的な要因が冷却性能に影響を与えることを、彼らは実証しました。
熱伝導率の「真実」とPCER24の哲学
動画の元々の説明文にもあるように、PCER24は以前から「CPUグリスの熱伝導率の疑惑」というテーマで別の動画(https://youtu.be/tuvWGKg5oTQ)を公開しています。これは、メーカーが公表する熱伝導率の数値が、必ずしも実際の冷却性能を正確に反映していないという彼らの見解を示しています。
今回のPS5の検証結果は、まさにその哲学の延長線上にあると言えるでしょう。数値上のスペックに囚われず、実際の使用環境でのパフォーマンスと、長期的な安定性・メンテナンス性を重視するPCER24の姿勢が、この動画全体から強く伝わってきます。彼らは単に修理を行うだけでなく、ユーザーが安心して長く機器を使えるための最適なソリューションを追求しているのです。
チャンネル「PCER24」について深掘り
今回の動画を投稿したYouTubeチャンネル「PCER24」は、PCやゲーム機の修理、メンテナンス、カスタムに関する深い知識と実践的な技術を持つプロフェッショナル集団です。彼らの動画は、単なる修理手順の紹介にとどまらず、なぜその作業が必要なのか、その技術的な背景はどうなっているのか、といった本質的な部分まで踏み込んで解説してくれるのが特徴です。
「PCER24」の動画は、専門的な内容を分かりやすく、そして時にはユーモアを交えながら解説してくれるため、初心者からベテランまで幅広い層の視聴者に支持されています。彼らは、既成概念にとらわれず、常に新しい検証や改善策を模索する探求心を持っており、その姿勢は、今回のPS5液体金属検証動画にも如実に表れています。
また、彼らは単に情報を提供するだけでなく、LGA1700用CPU固定金具「Anti Bent Cool Booster」やNintendo Switch用「ゲームカードスロットクリーナー」といった、独自の視点から開発した製品を販売している点も注目に値します。これは、彼らが単なるコンテンツクリエイターではなく、実際に現場で培った知識と技術を形にしている証拠であり、その技術力と信頼性の高さを裏付けています。PCER24は、まさに「実践する技術者」としての魅力を放つチャンネルと言えるでしょう。
関連情報と背景
PS5における液体金属の採用は、ソニーが従来のCPUグリスでは達成できなかった冷却性能を追求した結果です。しかし、液体金属は電気を通す性質があり、取り扱いには非常に高い専門性が求められます。製造工程での精密な塗布や、経年劣化によるポンプアウト現象を防ぐための設計は、メーカーにとって大きな課題でした。
一方で、CPUグリスの技術も日々進化しています。今回の動画で使用されたArctic MX6のような高性能グリスは、優れた熱伝導率に加え、非導電性で扱いやすく、長期的な安定性にも優れています。PCER24の検証は、これらの高性能グリスが、特定の条件下では液体金属に匹敵する、あるいはそれ以上の実用的な冷却性能を発揮し得ることを示唆しています。これは、今後のゲーム機や高性能PCの冷却設計において、液体金属以外の選択肢がより現実的になる可能性を示唆する、非常に重要なデータと言えるでしょう。
視聴者の反応やコメントについて
動画のコメント欄には、PCER24の検証結果に対する驚きと感謝の声が多数寄せられています。「まさかグリスでここまでいけるとは!」「液体金属の不安が解消された」「プロの検証は説得力が違う」といったコメントが多く見られ、多くのPS5ユーザーが冷却性能や液体金属の安全性について潜在的な不安を抱えていたことが伺えます。
また、「自分のPS5もグリスに交換したい」「どのグリスを使えばいいか参考になった」といった、具体的な行動を促されるコメントも散見されます。PCER24の動画が、単なる情報提供に留まらず、視聴者の疑問を解消し、新たな選択肢を提示する役割を果たしていることが、これらのコメントから見て取れます。
まとめと次のステップ
「PS5液体金属はもう不要?CPUグリスに替えたプロの衝撃検証【冷却性能の真実】」と題した今回の記事では、PCER24が公開した画期的な検証動画「PS5の液体金属…..とりあえずやめますわ~!~PS5をCPUグリスにしてみたって話!~」を深く掘り下げてきました。この動画は、PS5に標準採用されている液体金属の冷却性能が、適切な高性能CPUグリスによって十分に代替可能であることを、具体的なデータとプロの視点から実証しました。
液体金属の持つ潜在的なリスクやメンテナンスの難しさを考慮すると、今回の検証結果は、PS5の長期的な運用やメンテナンスを考える上で非常に重要な示唆を与えてくれます。「熱伝導率の数値だけが全てではない」というPCER24の哲学は、私たちがデバイスの性能を評価する上で、より多角的な視点を持つことの重要性を教えてくれます。
この記事を読んで、PS5の冷却性能の真実に興味を持たれた方は、ぜひ一度、PCER24のYouTubeチャンネルを訪れ、今回の検証動画を直接ご覧になることを強くお勧めします。そして、彼らの他の動画もチェックして、PCやゲーム機の奥深い世界に触れてみてください。きっと、あなたのデバイスに対する見方が変わるはずです。